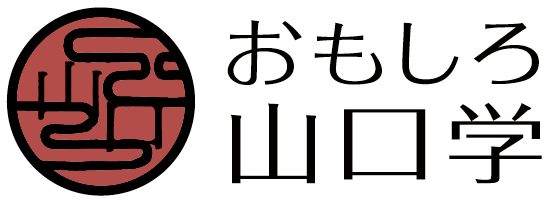

(左)「功山寺仏殿」(下関市)。仏殿は国宝。義長は弘治3(1557)年4月、この寺(当時は長福寺)で自刃した。(右)周南市にある陶氏の本城「若山城跡」の桜。晴賢への顕彰活動によって370本近い桜が植樹されている
さらば!! 西国一の大名・大内氏「最後の当主」大内義長
えっ“偽主”!? 後の歴史観が影響して…


「瑠璃光寺五重塔」(山口市)。国宝。14世紀末、大内義弘(よしひろ)は最高権力者だった足利義満(よしみつ)に対して挙兵し、敗死。この五重塔は義弘の供養塔として嘉吉2(1442年)ごろ建立された。屋根は檜皮葺で、その曲線が美しく、大内氏の文化を代表する優美な塔として知られる
※Escキーで戻ります。
「瑠璃光寺五重塔」(山口市)。国宝。14世紀末、大内義弘(よしひろ)は最高権力者だった足利義満(よしみつ)に対して挙兵し、敗死。この五重塔は義弘の供養塔として嘉吉2(1442年)ごろ建立された。屋根は檜皮葺で、その曲線が美しく、大内氏の文化を代表する優美な塔として知られる
※写真をクリックで拡大。Escキーで戻ります。


古写真「大寧寺(長門市深川)」(山口県文書館蔵)。撮影年不明。クーデターの際、大内義隆はこの寺で自刃。義長は兵火を被った寺の復興に着手したといい、引き続き毛利氏が復興。陶氏と姻戚関係にあった益田(ますだ)氏が山門を寄進し、毛利氏は義隆三十三回忌を行った。後に山門は焼失し、再建されたが明治時代に倒壊し、礎石(写真手前)が現在も残る。寺の背後に義隆らの墓所がある
※Escキーで戻ります。
古写真「大寧寺(長門市深川)」(山口県文書館蔵)。撮影年不明。クーデターの際、大内義隆はこの寺で自刃。義長は兵火を被った寺の復興に着手したといい、引き続き毛利氏が復興。陶氏と姻戚関係にあった益田(ますだ)氏が山門を寄進し、毛利氏は義隆三十三回忌を行った。後に山門は焼失し、再建されたが明治時代に倒壊し、礎石(写真手前)が現在も残る。寺の背後に義隆らの墓所がある
※写真をクリックで拡大。Escキーで戻ります。


「大内義長書状」(山内家文書 山口県文書館蔵)。毛利氏は義長を擁して陶晴賢を討ちたいと考え、義長と晴賢の仲を裂こうと画策した。この書状は天文23(1554)年5月、毛利氏が大内氏・陶氏に対して挙兵した約半月後、義長が、疑心暗鬼になった晴賢に、裏切ろうとする心はないことを誓ったもの
※Escキーで戻ります。
「大内義長書状」(山内家文書 山口県文書館蔵)。毛利氏は義長を擁して陶晴賢を討ちたいと考え、義長と晴賢の仲を裂こうと画策した。この書状は天文23(1554)年5月、毛利氏が大内氏・陶氏に対して挙兵した約半月後、義長が、疑心暗鬼になった晴賢に、裏切ろうとする心はないことを誓ったもの
※写真をクリックで拡大。Escキーで戻ります。


「弾正糸桜」(周南市鹿野総合支所提供)。周南市鹿野総合支所のそば、陶氏の有力家臣・江良(えら)氏(弾正忠)の居館跡と伝わる地にある。厳島の戦い後、毛利氏の周防国侵攻が進む中、江良氏は須々万城(周南市)を守って激しく抵抗したが、最終的に毛利氏に下った。なお、桜の開花は例年4月初旬から中旬まで
※Escキーで戻ります。
「弾正糸桜」(周南市鹿野総合支所提供)。周南市鹿野総合支所のそば、陶氏の有力家臣・江良(えら)氏(弾正忠)の居館跡と伝わる地にある。厳島の戦い後、毛利氏の周防国侵攻が進む中、江良氏は須々万城(周南市)を守って激しく抵抗したが、最終的に毛利氏に下った。なお、桜の開花は例年4月初旬から中旬まで
※写真をクリックで拡大。Escキーで戻ります。


「勝山城跡遠景」(下関市教育委員会提供)。右奥の山が、勝山城があった山。義長は重臣の内藤隆世(ないとう たかよ)らと共に山口を逃れ、勝山城に籠城。防御に優れた山城で、毛利方を苦しめた。その後、義長は長福寺(現在の功山寺)へ
※Escキーで戻ります。
「勝山城跡遠景」(下関市教育委員会提供)。右奥の山が、勝山城があった山。義長は重臣の内藤隆世(ないとう たかよ)らと共に山口を逃れ、勝山城に籠城。防御に優れた山城で、毛利方を苦しめた。その後、義長は長福寺(現在の功山寺)へ
※写真をクリックで拡大。Escキーで戻ります。


「大内義長の墓と伝わる宝篋印塔」(下関市)。功山寺仏殿の裏、墓地の一角にある。江戸時代にはすでに伝承となり、確かに義長の墓か、分からなくなっていた。江戸時代中期の「新裁軍記」では、義長十七回忌に当たって元就の孫・輝元(てるもと)から長福寺(現在の功山寺)に米銭が渡されていることから、やはりここが埋葬の地、としている
※Escキーで戻ります。
「大内義長の墓と伝わる宝篋印塔」(下関市)。功山寺仏殿の裏、墓地の一角にある。江戸時代にはすでに伝承となり、確かに義長の墓か、分からなくなっていた。江戸時代中期の「新裁軍記」では、義長十七回忌に当たって元就の孫・輝元(てるもと)から長福寺(現在の功山寺)に米銭が渡されていることから、やはりここが埋葬の地、としている
※写真をクリックで拡大。Escキーで戻ります。
- クーデター時の名は陶隆房(たかふさ)。おもしろ山口学「本当に逆臣?! 陶晴賢の虚像。そして今」参照。

- おもしろ山口学「大内義隆の栄華と悲劇 第1回 文書から浮かぶ大内義隆の人物像」参照。

- 他にも諸説がある。

- 養子縁組解消の恥をそそぎたいという願文を宇佐宮(宇佐八幡宮)に納めた。大分県史料刊行会『大分県史料 第24』。

- 大内氏の祖とされる百済国の琳聖太子(りんしょうたいし)は多々良浜に上陸したとされる。海路を勧めたのは兄・宗麟。

- 東京大学出版会『大日本古文書 家わけ第二十一 蜷川家文書之三』。

- 「フロイス日本史」『山口県史料 中世編 上』。

- 「聖フランシスコ・ザビエル全書簡」『山口市史 史料編 大内文化』。

- 「フロイス日本史」『山口県史料 中世編 上』。

- 吉見正頼(よしみ まさより)。正室は大内義隆の姉。

- 弘中隆兼(たかかね)。おもしろ山口学「大内氏・陶氏VS毛利氏 厳島の戦い 第1回 兵力差の真実と、手紙が残した真実」「第2回 陶晴賢らの渡海と、渡海に反対した弘中隆兼の最期」参照。

- おもしろ山口学「厳島の戦い-大内氏重臣・弘中隆兼 最後の手紙-」参照。

- おもしろ山口学「大内義隆の栄華と悲劇 第2回 重臣らによるクーデターと毛利元就」参照。

- その後、大内氏・陶氏と毛利氏が敵味方に分かれる「防芸引分」と記すようになった。

- 江戸時代中期、萩藩士・永田政純(ながた まさずみ)がまとめた「新裁軍記」による。なお、弑逆とは、君主や父を殺害すること。天誅とは、天に代わって罰を与えること。

- 「新裁軍記」による。義旗とは、正義のための戦いに揚げる旗。

- 近藤清石『大内氏実録』。御薗生翁甫『大内氏史研究』では「偽主」とする。

下関市立歴史博物館 企画展「『英雄』の素顔-武将たちの虚像と実像-」
「謀略家」のイメージが広まっている毛利元就など、後に英雄とされた武将たちについて、物語や伝承で語られる姿を紹介するとともに、信頼のおける資料から実際の姿に迫る展示です。
開催期間 4月2日(日曜日)まで
毛利博物館 毛利元就郡山入城500年記念 企画展「元就入城」
元就が安芸国の郡山城(現在の広島県安芸高田市)に入城して今年で500年。それを記念し、毛利家伝来の貴重な史料を通して、大江広元(おおえのひろもと)から元就までの毛利家の歴史を紹介する企画展です。
開催期間 4月22日(土曜日)から5月28日(日曜日)まで
参考文献
- 大分県史料刊行会『大分県史料 第24』1964
- 鹿毛敏夫『大友義鎮-国君、以道愛人、施仁発政-』(ミネルヴァ日本評伝選) 2021
- 近藤清石『大内氏実録』1885(1974復刻)
- 下関市立歴史博物館編『特別展 大内氏の興亡と毛利氏の隆盛-海峡の戦国史第1章-』2018
- 世良莞一・大庭龍偲編『曹洞宗瑞雲山大寧護国禅寺略史』2010(増補改訂)
- 田村哲夫校訂『新裁軍記』1993
- 東京大学出版会『大日本古文書 家わけ第二十一 蜷川家文書之三』1987
- 東京大学出版会『大日本古文書 家わけ第二十二 益田家文書之五』2021
- 長谷川泰志「厳島合戦と軍記物語-毛利氏関係軍記を中心に-」『広島経済大学研究論集』第41巻 2018
- 藤井崇『大内義隆-類葉武徳の家を称し、大名の器に載る-』(ミネルヴァ日本評伝選) 2019
- 三坂圭治校注『戦国期 毛利氏史料撰』1987
- 御薗生翁甫『大内氏史研究』1959
- 御薗生翁甫「新撰大内氏系図」『近世防長諸家系図綜覧』1980
- 山口県編『山口県史 通史編 中世』2012
- 山口県文書館編『防長寺社由来』7 1985
- 山口県文書館編『防長風土注進案』19 1962
- 山口県文書館編『山口県史料 中世編 上』1979
- 山口市交流創造部文化交流課・網野ゆかり編『西国一の御屋形様 大内氏がわかる本 入門編』2021
- 山口市交流創造部文化交流課・網野ゆかり編『西国一の御屋形様 大内氏がわかる本 興亡編』2022
- 山口市編『山口市史 史料編 大内文化』2010
- ルイス・フロイス(柳谷武夫 訳)『日本史1 キリシタン伝来のころ』(東洋文庫 4) 1963
- 和田秀作「大内氏の惣庶関係をめぐって」『大内と大友-中世西日本の二大大名-』2013 など
おもしろ山口学バックナンバー
- 山口の守護大名 大内氏 第1回 栄華の軌跡(2010年8月13日)
- 鷲頭弘忠と上杉憲実と「大寧寺」(2012年9月28日)
- 大内義隆の栄華と悲劇 第2回 重臣らによるクーデターと毛利元就(2012年10月26日)
- 大内義興と足利義稙 第1回 周防国で8年暮らした流浪の足利将軍(2013年2月22日)
- 大内義興と足利義稙 第2回 船岡山の戦いと、将軍の政権を支えた義興(2013年3月8日)
- 大内輝弘「大内氏再興」の夢 第1回 「山口の正統の王」(2013年10月11日)
- 大内輝弘「大内氏再興」の夢 第2回 輝弘の夢が残したもの(2013年10月25日)
- 国宝「瑠璃光寺五重塔」はなぜ美しいのか(2019年8月23日)
- 瓦が物語る、失われた凌雲寺の謎-大内氏遺跡指定60周年- (2019年9月27日)
- もう一つの応仁・文明の乱-大内政弘VS大内道頓-(2019年10月25日)
- 中国地方の覇者 毛利元就。あの“三本の矢”の真実とは?! (2021年8月27日)
- 見えてきた!! 謎多き大内氏遺跡「築山跡」(2022年9月22日)