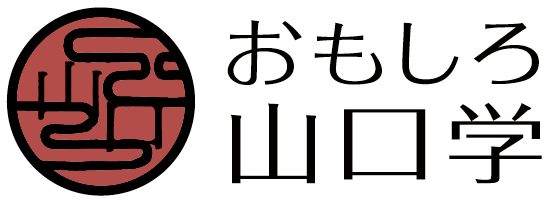

(左)「築山跡史跡公園」(山口市教育委員会提供)。(右)「山口町村図」(部分)(山口県文書館蔵)。幕末の文久3(1863)年ごろ、萩藩が作製した絵図。築山跡が「ツキ山」と記され、築地跡の石垣なども描かれている。築山跡には江戸時代の安政3(1856)年、落雷で焼失した月見松があったといい、その跡も描かれている
見えてきた!! 謎多き大内氏遺跡「築山跡」
築山跡は別邸跡ではなく、隠居した教弘が短期間居館とした地だった!!


「行程記」(部分)(山口県文書館蔵)。行程記は明和元(1764)年ごろ、萩藩が作製した街道絵図。築山跡は「築山」として、赤い引き出し線の先には「世俗の説」と「教弘を築山殿とも言うとのこと。よって、ここを築山と言うとのこと」とある。二方向(西と北)に築地も描かれ「石垣高さ一丈」とある
※Escキーで戻ります。
「行程記」(部分)(山口県文書館蔵)。行程記は明和元(1764)年ごろ、萩藩が作製した街道絵図。築山跡は「築山」として、赤い引き出し線の先には「世俗の説」と「教弘を築山殿とも言うとのこと。よって、ここを築山と言うとのこと」とある。二方向(西と北)に築地も描かれ「石垣高さ一丈」とある
※写真をクリックで拡大。Escキーで戻ります。


「山口町村図」(部分)(山口県文書館蔵)。文久3(1863)年ごろ、萩藩が作製した絵図。現在は築山跡にある築山神社(元は宝現霊社)は幕末、多賀社東の後河原片岡(山口県警察体育館 旧武徳殿辺り)にあったことがこの絵図からも分かる。また八坂神社が、かつては一時、五重塔近くにあったことも分かる。山口屋形は現在の山口県庁の地
※Escキーで戻ります。
「山口町村図」(部分)(山口県文書館蔵)。文久3(1863)年ごろ、萩藩が作製した絵図。現在は築山跡にある築山神社(元は宝現霊社)は幕末、多賀社東の後河原片岡(山口県警察体育館 旧武徳殿辺り)にあったことがこの絵図からも分かる。また八坂神社が、かつては一時、五重塔近くにあったことも分かる。山口屋形は現在の山口県庁の地
※写真をクリックで拡大。Escキーで戻ります。


「築地跡」(山口市教育委員会提供)。築山跡の北西隅にかつての築地(土塁)が現存。「大内氏掟書」には築地の上で祇園会の見物を禁じることが記されている。また萩藩が幕末、山口へ本拠を移して居城(現在の山口県庁の地)を築いた際、その石垣が一部転用されたという。さらに築地跡の上の全長4メートルの石塀は、江戸時代の『防長風土注進案』によれば「築山大明神の旧跡」とされる
※Escキーで戻ります。
「築地跡」(山口市教育委員会提供)。築山跡の北西隅にかつての築地(土塁)が現存。「大内氏掟書」には築地の上で祇園会の見物を禁じることが記されている。また萩藩が幕末、山口へ本拠を移して居城(現在の山口県庁の地)を築いた際、その石垣が一部転用されたという。さらに築地跡の上の全長4メートルの石塀は、江戸時代の『防長風土注進案』によれば「築山大明神の旧跡」とされる
※写真をクリックで拡大。Escキーで戻ります。


「八坂神社」(山口市教育委員会提供)。築山跡にある神社の一つ。大内弘世が京都から勧請したと伝わる。当初は竪小路にあったとされ、瑠璃光寺五重塔近くの水の上、高嶺太神宮(現在の山口大神宮)のそばへと移り、元治元(1864)年に築山跡へ。本殿は永正17(1520)年、大内義興が建てたもので国の重要文化財
※Escキーで戻ります。
「八坂神社」(山口市教育委員会提供)。築山跡にある神社の一つ。大内弘世が京都から勧請したと伝わる。当初は竪小路にあったとされ、瑠璃光寺五重塔近くの水の上、高嶺太神宮(現在の山口大神宮)のそばへと移り、元治元(1864)年に築山跡へ。本殿は永正17(1520)年、大内義興が建てたもので国の重要文化財
※写真をクリックで拡大。Escキーで戻ります。
- 館跡・築山跡・高嶺城跡・凌雲寺跡。

- 現在の龍福寺の地。おもしろ山口学「大内氏館と庭園(前編)」「大内氏館と庭園(後編)」
 参照。
参照。
- 料亭「祇園菜香亭」(現在は山口市菜香亭として近くの地へ移転)があった地なども含む。

- 『防長風土注進案』や『大内家古実類書』など。

- 昭和50年代以降、平成26(2014)年度までに15次にわたる調査を実施。その後、史跡整備が行われ、今年10月、「築山跡史跡公園」として開園。

- 第1段階は、14世紀末から15世紀前半で、土地は活発な利用がない段階。

- 川岡勉「第3章 大内氏と周防・長門」『山口県史 通史編 中世』2012など。

- 発掘調査で池泉庭園の跡は見つかっていない。

- 山口市大内御堀にあり、中世には大内氏の氏寺としてあつく信仰され、谷全体に多くの坊舎があった。

- 山王社は日吉(ひえ)山王権現を祀る神社。

- 神社や寺院に寄付すること。

- 南北朝時代、大内弘世(ひろよ)が京都から勧請したと伝わる。当初は竪小路にあったとされ、水の上、高嶺太神宮(現在の山口大神宮)のそばへと移り、元治元(1864)年に現在地へ。

- 歴代当主の中で最も栄華を誇った。

- 移転の経緯には諸説ある。一説として、龍福寺境内に義隆を祀る社はあったが、慶長年間に多賀神社境内へ移り、再び龍福寺境内、後河原片岡へと移り、明治初期に現在地で築山神社と改称(『大内氏館跡12』2011,『大内氏遺跡調査資料』1960など)。別の説として、多賀神社境内に創建され、龍福寺境内、後河原片岡、現在地へ(『防長風土注進案』第13巻 1964など)。なお、龍福寺境内にも現在、宝現霊社がある。また、現在の雲谷庵(明治時代の再建)には、かつての宝現霊社拝殿の柱が使われている。おもしろ山口学「雪舟のアトリエ『雲谷庵』と、庵を甦らせた近藤清石」参照。

ぐるり! 大内文化ゾーン 築山跡史跡公園オープン記念事業
築山跡史跡公園が10月10日(月曜日・祝日)に開園することを記念し、大内氏ゆかりの史跡や文化財などが多く残る「大内文化ゾーン」でさまざまな関連イベントなどが行われます。
開催期間:12月まで
場所:市内各地(大内文化ゾーン)
参考文献
- 乾貴子「戦国期山口城下における城館と屋敷神-周防国守護所別邸『築山』について-」『山口県地方史研究』第74号 1995
- 古賀信幸「大内氏遺跡築山跡小考」『山口考古』第34号 山本一朗先生追悼号 2014
- 高橋研一「戦国大名毛利氏の防長支配と元亀三年龍福寺『再興』」『山口県地方史研究』第99号 2008
- 御薗生翁甫『防長地名淵鑑』1974
- 百田昌夫「十五世紀後半の周防守護所-二つの会席・二つの郭をめぐって」『山口県史研究』3 1995
- 山口県文書館編『防長風土注進案』第13 巻 山口宰判下 1964
- 山口県編『山口県史 通史編 中世』2012
- 山口県文書館編『絵図でみる防長の町と村』1989
- 山口市教育委員会編『大内氏遺跡調査資料』1960
- 山口市教育委員会編『大内氏館跡12』2011
- 山口市教育委員会編『大内氏築山跡8』(大内氏遺跡発掘調査報告24)2016
- 山口市教育委員会編『史跡大内氏遺跡保存活用計画-第1次改訂-』2019
- 山口市文化交流課「特集1『築山跡史跡公園』開園-大内教弘と築山-」『山口ヒストリア』2022 など



