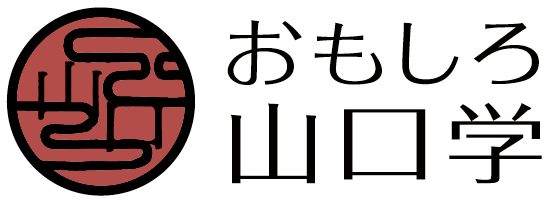

「矢嶋邸写真」(部分)(下松市郷土資料展示収蔵施設「島の学び舎」蔵)。手前は塩田。その向こうに矢嶋邸の白壁や門が見える
矢嶋作郎・矢島専平と、ものづくりのまち下松
第2回 矢島専平と、久原房之助の「下松大工業都市建設計画」
未完に終わった壮大な夢から生まれた、ものづくりのまち


「覧海軒図」(山口県立山口博物館蔵)。宮洲屋(磯部家)の別邸「覧海軒」が描かれた江戸時代の絵図。二階から海や塩田を眺める人々や、塩田で塩づくりに従事する人々などが克明に描かれている
Escキーで戻ります。
「覧海軒図」(山口県立山口博物館蔵)。宮洲屋(磯部家)の別邸「覧海軒」が描かれた江戸時代の絵図。二階から海や塩田を眺める人々や、塩田で塩づくりに従事する人々などが克明に描かれている
※写真をクリックで拡大。Escキーで戻ります。


国指定重要文化財「三角縁盤龍鏡」(東京国立博物館蔵)出典:ColBase (https://colbase.nich.go.jp/)。宮洲屋が享和2(1802)年、宮ノ洲山近くの松林を開作中、宮ノ洲古墳を発見。石室から三角縁盤龍鏡など中国製3面・日本製1面の青銅鏡などが出土した。一帯が工場用地となり、古墳は昭和27(1952)年、消滅した。古墳の被葬者は、貴重な中国製鏡を3面も持っていたことから、瀬戸内海の海上交通に深く関わり、畿内の勢力と密接な関係を持った豪族と考えられている
Escキーで戻ります。
国指定重要文化財「三角縁盤龍鏡」(東京国立博物館蔵)出典:ColBase (https://colbase.nich.go.jp/)。宮洲屋が享和2(1802)年、宮ノ洲山近くの松林を開作中、宮ノ洲古墳を発見。石室から三角縁盤龍鏡など中国製3面・日本製1面の青銅鏡などが出土した。一帯が工場用地となり、古墳は昭和27(1952)年、消滅した。古墳の被葬者は、貴重な中国製鏡を3面も持っていたことから、瀬戸内海の海上交通に深く関わり、畿内の勢力と密接な関係を持った豪族と考えられている
※写真をクリックで拡大。Escキーで戻ります。


「矢嶋邸水彩画 矢嶋邸の門」(下松市郷土資料展示収蔵施設「島の学び舎」蔵)。専平が屋敷地を手放すに当たり、専平から依頼された画家・小林重三(こばやし しげかず)が大正12(1923)年ごろ描いたもの。なお、矢嶋邸は現存しない。現在は東洋鋼鈑株式会社下松事業所の敷地内、大谷川と県道笠戸島公園線に挟まれた一画。老松が往時をしのばせる
※Escキーで戻ります。
「矢嶋邸水彩画 矢嶋邸の門」(下松市郷土資料展示収蔵施設「島の学び舎」蔵)。専平が屋敷地を手放すに当たり、専平から依頼された画家・小林重三(こばやし しげかず)が大正12(1923)年ごろ描いたもの。なお、矢嶋邸は現存しない。現在は東洋鋼鈑株式会社下松事業所の敷地内、大谷川と県道笠戸島公園線に挟まれた一画。老松が往時をしのばせる
※写真をクリックで拡大。Escキーで戻ります。


「矢嶋邸水彩画 弁財天社」(下松市郷土資料展示収蔵施設「島の学び舎」蔵)。邸内には、弁財天社があった。江戸時代の絵図「東西豊井村地下図」(山口県文書館蔵)にも、磯部家の別邸敷地内に弁財天社は描かれている。なお、小林重三は図鑑などに優れた鳥類画などを描いた画家
※Escキーで戻ります。
「矢嶋邸水彩画 弁財天社」(下松市郷土資料展示収蔵施設「島の学び舎」蔵)。邸内には、弁財天社があった。江戸時代の絵図「東西豊井村地下図」(山口県文書館蔵)にも、磯部家の別邸敷地内に弁財天社は描かれている。なお、小林重三は図鑑などに優れた鳥類画などを描いた画家
※写真をクリックで拡大。Escキーで戻ります。


「矢嶋邸水彩画 大坂城残石の庭石」(下松市郷土資料展示収蔵施設「島の学び舎」蔵)。矢嶋邸内には大坂城築城の残石が二つあった。その一つは専平が昭和5(1930)年、現在の山口県立山口博物館へ寄贈(現在、前庭にある)。残石は大津島(現在の周南市)で切りだされたもので、毛利輝元(もうり てるもと)による豊臣秀吉の大坂城築城時の石と伝えられてきたが、近年、毛利秀就(ひでなり)による徳川氏の大坂城普請時の石と考えられる
※Escキーで戻ります。
「矢嶋邸水彩画 大坂城残石の庭石」(下松市郷土資料展示収蔵施設「島の学び舎」蔵)。矢嶋邸内には大坂城築城の残石が二つあった。その一つは専平が昭和5(1930)年、現在の山口県立山口博物館へ寄贈(現在、前庭にある)。残石は大津島(現在の周南市)で切りだされたもので、毛利輝元(もうり てるもと)による豊臣秀吉の大坂城築城時の石と伝えられてきたが、毛利秀就(ひでなり)による徳川氏の大坂城普請時の石と考えられる
※写真をクリックで拡大。Escキーで戻ります。
- おもしろ山口学「矢嶋作郎・矢島専平と、ものづくりのまち下松 第1回 “日本初の近代的紙幣”造りと“日本初の電力会社”に関わった矢嶋作郎と渋沢栄一」参照。

- 下松の有力町人だった磯部(いそべ)家の当主が、家督を長男に譲った後、次男と共に興した分家の屋号。

- 古川古松軒(ふるかわ こしょうけん)の紀行文『西遊雑記(さいゆうざっき)』。

- 日立鉱山の開発者で、久原鉱業所を設立し、第一次世界大戦中、巨利を築くが大戦後、事業が悪化。経営再建を妻の兄、山口出身の鮎川義介(あゆかわ よしすけ)に託し、政界へ転じた。

- 琵琶湖疏水(びわこそすい)などの土木事業、小坂鉱山などの鉱山経営、関西電力の創立など、多彩な事業を展開し、藤田財閥を築いた実業家。

- 当時の下松町・末武南村・末武北村・久保村(現在の下松市)、太華村・久米村(現在の周南市)。

- 専平が昭和14(1939)年、下松町など1町3村が合併して下松市が誕生する直前にまとめた手記『秋の夜話(やわ)』。引用は『復刻版 秋の夜話』より。

- 川崎車輛株式会社の車輛課長だった古山石之助(ふるやま いしのすけ)を所長として迎えた。

- 2月、日立製作所の付属工場となり、5月、株式会社日立製作所笠戸工場となった。

- 現在の社名は株式会社日立製作所鉄道ビジネスユニット笠戸事業所。

下松市立図書館 下松市郷土資料・文化遺産デジタルアーカイブ
宮ノ洲の塩田を描いた江戸時代の絵図や、矢嶋邸を写した古写真など、貴重な史料をインターネット上で閲覧できます。また、かつての矢嶋邸(現存しない)を大正12(1923)年ごろに描いた貴重な水彩画なども先日新たに追加されました。
参考文献
- 荒巻直大「山口県立山口博物館所蔵大坂城築城の残石について」『山口県立山口博物館研究報告』43 2017
- 笠戸工場史編集室『日立製作所笠戸工場史』1975
- 下松市『下松市史』1989
- 下松市『復刻版 秋の夜話』2019
- 下松市立図書館「下松で古地図さんぽ」2020
- 久原房之助翁伝記編纂会『久原房之助』1970
- 砂川幸雄『藤田伝三郎の雄渾なる生涯』1999
- 宮田幸治『宮ノ洲古墳-その発見から消滅まで-』2015
- 矢島雅子『矢嶋作郎翁 下松旧邸画集』2017 など

