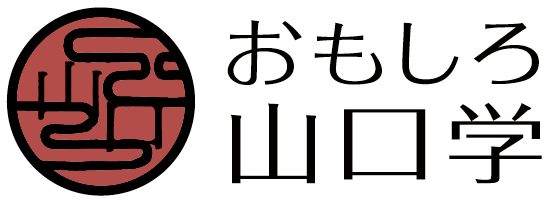

山あいにある岩国市六呂師、梅雨左衛門の伝承がある地域の写真(金谷匡人氏提供)。約20年前に撮影。道のそばにそびえる大岩(烏帽子岩(えぼしいわ))に梅雨左衛門がすむという伝承がある。辺りには棚田が広がっている
梅雨を操る「梅雨左衛門」
タブーあり。触らぬ神にたたりなし!?


令和元(2019)年7月の六呂師、大岩周辺の風景(金谷匡人氏提供)。棚田の耕作は行われなくなっており、中央あたりに大岩があるが、遠くからではやぶに覆われて見えない
※Escキーで戻ります。
令和元(2019)年7月の六呂師、大岩周辺の風景(金谷匡人氏提供)。棚田の耕作は行われなくなっており、中央あたりに大岩があるが、遠くからではやぶに覆われて見えない
※写真をクリックで拡大。Escキーで戻ります。


国の天然記念物「岩国のシロヘビ」。伝承の梅雨左衛門とは異なるが、岩国には、限られた地域に何世代にもわたって集団で生息する、世界的に貴重なシロヘビが存在し、保護活動が行われている。アオダイショウの突然変異で、長さ180センチメートルにもなる。弁財天の使いともされ、民間信仰の対象
※Escキーで戻ります。
国の天然記念物「岩国のシロヘビ」。伝承の梅雨左衛門とは異なるが、岩国には、限られた地域に何世代にもわたって集団で生息する、世界的に貴重なシロヘビが存在し、保護活動が行われている。アオダイショウの突然変異で、長さ180センチメートルにもなる。弁財天の使いともされ、民間信仰の対象
※写真をクリックで拡大。Escキーで戻ります。


「岩国シロヘビの館」。岩国のシロヘビの生態展示のほか、映像やゲームなどを通じて、岩国のシロヘビの生態や歴史を学習できる。また、岩国各地の梅雨左衛門について紹介したパネルも展示されている。
※Escキーで戻ります。
「岩国シロヘビの館」。岩国のシロヘビの生態展示のほか、映像やゲームなどを通じて、岩国のシロヘビの生態や歴史を学習できる。また、岩国各地の梅雨左衛門について紹介したパネルも展示されている。
※写真をクリックで拡大。Escキーで戻ります。


「ギンリョウソウ(銀龍草)」(金谷匡人氏提供)。日本国語大辞典によれば、異名は「露左衛門(つゆざえもん)」。高さ約10センチメートル。山中の日陰、湿り気のあるところで、堆積した落ち葉などに生える。花やうろこ状の葉も白く半透明で、5月から8月ごろの梅雨時に花を咲かせる。「幽霊茸(ユウレイダケ)」ともいう
※Escキーで戻ります。
「ギンリョウソウ(銀龍草)」(金谷匡人氏提供)。『日本国語大辞典』によれば、異名は「露左衛門(つゆざえもん)」。高さ約10センチメートル。山中の日陰、湿り気のあるところで、堆積した落ち葉などに生える。花やうろこ状の葉も白く半透明で、5月から8月ごろの梅雨時に花を咲かせる。「幽霊茸(ユウレイダケ)」ともいう
※写真をクリックで拡大。Escキーで戻ります。
- 江戸時代の岩国は、吉川家の領地、岩国藩。岩国藩は毛利元就(もうり もとなり)の次男・吉川元春(きっかわ もとはる)の第三子・広家(ひろいえ)を初代とする。城主格を許され、正式に藩となったのは、明治元(1868)年。

- 岩国藩士の広瀬喜運(ひろせ きうん)が享和2(1802)年にまとめた地誌。

- シマヘビの黒色変種の俗称。

- 半夏生(はんげしょう)。夏至から11日目。太陽暦では7月2日ごろ。多くの村ではこの日までに田植えを終えることとされていた。

- 夜市(やじ)村(現在の周南市)にも梅雨左衛門の伝承がある。

- 島根県出雲地方では「ツユ神(じん)」と呼ばれ、梅雨の期間中、初めは頚(くび)を見せ、中頃には胴を見せ、終わりには尾を見せるという。また、島根県石見地方の「梅雨左衛門」には腰から下の病気に霊験があると伝わる。おねしょの治癒祈願もあるという。

- 萩藩が天保12(1841)年以降、藩内の各村にさまざまな情報を提出させたものをまとめた地誌。

- 午前8時ごろ。

- 昭和53(1978)年に岩国徴古館から、江戸時代の記録にある怪談などをまとめ『岩邑怪談録』の続編として刊行。この六呂師村の梅雨左衛門の話は、地元在住の方の民俗的メモ集から採り、整理されたもの。

- 夜市村の伝承では、梅雨左衛門をつつくと百日も梅雨が止まぬと恐れられていたという。

参考文献
- 石塚尊俊「ツユ神」『民間伝承』16巻8号 1952
- 岩国徴古館『享保増補村記』1989
- 岩国徴古館『続・岩邑怪談録』1978
- 金谷匡人「岩国の伝承 梅雨左衛門-梅雨を教える『白い小さな蛇』-」(岩国市民大学講座資料) 2019
- 『玖珂郡志』1975
- 夜市地区コミュニティ推進協議会『矢地から夜市へ』2015
- 山口県文書館「第10回中国四国地区アーカイブズウィーク 文書館動物記-書庫に棲む動物たち-」2015
- 山口県文書館『防長風土注進案』7 1963 など



